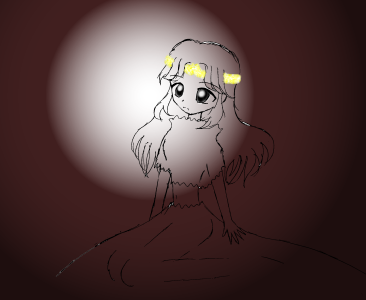|
第一章「必然の出逢い」
第一話・邂逅
「空、大きいな…」 青い空を見上げる度に、少女は思った。
「風、気持ちいいな…」 僅かに吹き込んでくる春風を感じる度に、少女は思った。
「太陽、月、綺麗だな…」 東から昇る時だけ見える太陽や月を眺める度に、少女は思った。
少女はずっと前からここにいた。 いつ出られるのかなんて分からなかった。 いや、それよりも。
外は見える。 けれど、いつからここにいるのか分からない少女にとっては……自分が外へ出る行為そのものが、よく分からなかった。 自分は果たして、外へ出たことがあるのだろうか?
答えは、ない。
言葉は知っている。 そして文字を読むことも、いちおう出来た。
けれど、言葉を知るのと、単語を知るのでは、違いすぎる。 それらは、彼女が閉じこめられている岩の内側に、絵と文字と共に描かれていた。
……それほどまでに、少女の知識は幼子のように乏しかった。
あまりにも。 一人で生きすぎていた。
でも……。
「何をしてるんだい?」
眠っていた少女に誰かが声をかけた。 が、彼女の覚醒ぶりと驚きようといったら、半端なものではなかった。 無理もない。
顔を上げると、そこには……一人の人間が立っていた。 といっても、少女は「人間」など知らない。 自分以外、知らないのだから。
けれど。 どんな空よりも大きく見えた。 その長くて紅い髪も。 不思議そうに、けれど微笑みを浮かべた、優しげな表情も。
少女は思わず見とれた。 しかし、それは驚きだけではなかった。 そう、懐かしいものを感じていた。 初めて見るはずなのに。 ずっと前から知っていたような……。
「ずっとここにいるの?」 「どれくらい前から?」 「ずっとずっと前から?」 「君、一人?」 「他には誰もいない?」 「ここで何をしているんだい?」 「ここにいて楽しい?」
少女はぼんやりとした頭のまま、ほとんど反射的に答えていた。 答えのあるなしに関わらず、反射で答えが出なければ、黙っていた。 人間はそんな少女に、嫌な顔一つしなかった。 牢の外に腰掛けて、色んな質問を投げかける。
「好きなものは何?」 「あれ、好き?」 東の空を照らす太陽を見つめながら、人間はまたいろいろなことを語った。 「あれは好き?」 「そう。綺麗だよね」 「月と太陽が仲良しだから」 「そうだね。でも、同じ蒼空にいるんだよ。離れていてもね」 人間と語っていくうちに、少女は知らず知らず、喋る言葉を増やしていた。 段々と言葉遣いも流暢になっていく。
そして……再び、太陽が、昇った。
少女はその日、一睡もしていなかった。 いつもは月が見えなくなった辺りで眠ってしまっていたのに。
この日の晩、彼女は寸部の眠気も感じず……太陽が昇る瞬間を見たのだった。
|